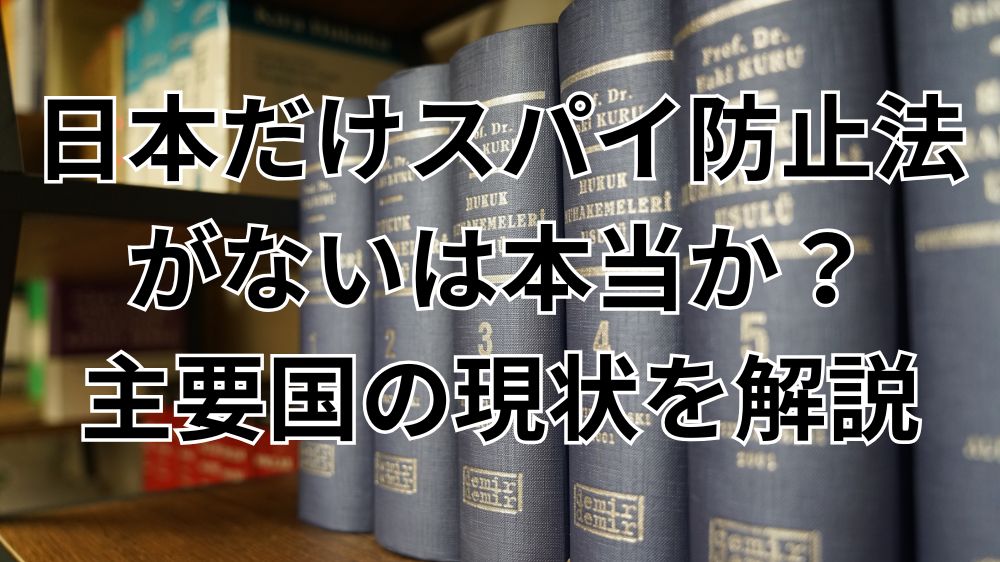「日本だけスパイ防止法がない」──
そんな現状に、疑問の声が高まっています。
2025年7月、参政党の神谷宗幣代表が記者会見で発言しました。
秋の臨時国会に「スパイ防止法案」を提出する方針です。
外国勢力による情報の侵略。
日本の安全保障が揺らぐ中、ようやく法整備が動き始めようとしています。
本記事では、「スパイ防止法とは何か」「なぜ日本だけないのか」を中心に解説します。
各国の状況や、今後の論点もわかりやすく紹介します。
参政党がスパイ防止法案提出へ
参政党の神谷宗幣代表は、2025年7月22日の記者会見で、スパイ防止法案を秋の臨時国会に提出する方針を明らかにしました。
現在、法案の具体的な内容を検討中です。
参政党は、2025年7月の参院選で14議席を獲得し、単独でも法案提出が可能な数に達しました。
このことから、スパイ防止法案の国会提出が一段と現実味を帯びています。
さらに神谷代表は、他党とも連携して、より幅広い支持を得たうえでのスパイ防止法案の成立を目指すと語っています。
日本だけスパイ防止法がないって本当?
スパイ防止法が存在しない現状
日本には現在、スパイ防止法と呼ばれる法律が存在しません。
スパイ行為そのものを直接的に処罰する規定がないのです。
一応、「特定秘密保護法」や「破壊活動防止法」などで、機密漏洩や外患誘致に対応しています。
しかし、これらは一部のケースに限られ、スパイ防止法のような包括的な法律とは言えません。
実際、G7をはじめとする主要先進国の中で、スパイ防止法がないのは日本だけだと指摘されています。
専門家の間でも、「日本は法の空白状態にある」との懸念が広がっています。
過去に廃案となった法案の内容
1985年、自民党は「国家秘密に係るスパイ行為等の防止に関する法律案」を国会に提出。
いわゆるスパイ防止法案として、当時大きな注目を集めました。
この法案では、防衛や外交に関わる国家機密の漏洩、外国勢力への情報提供などが処罰対象とされていました。
しかし、国家秘密の定義があいまいで、恣意的な運用が可能になるという懸念が広がりました。
その結果、強い反対世論を受け、法案は審議未了のまま廃案となりました。
再び高まる法整備の機運
近年、外国勢力によるサイバー攻撃や情報流出が増えています。
ハイブリッド戦と呼ばれる、軍事・経済・世論操作を組み合わせた新たな脅威も深刻です。
こうした中で、「日本もスパイ防止法を整備すべきだ」という声が強まっています。
2025年の参議院選挙では、参政党や国民民主党がスパイ防止法の制定を公約に掲げて躍進。
自民党や日本維新の会も、法整備に前向きな姿勢を見せています。
今後、国会で法案が提出されれば、スパイ防止法の実現が一気に現実味を帯びてきます。
スパイ防止法とは何か?
スパイ行為とはどのようなものか
スパイ行為とは、本来守られるべき国家機密を、許可なく入手・漏洩・通報する行為です。
防衛・外交・技術情報などが対象となり、他国の利益のために行われることがほとんどです。
近年は、サイバー攻撃や経済スパイも含まれ、形を変えながら拡大しています。
1985年法案の中身と問題点
1985年、自民党が提出したスパイ防止法案では、国家機密の漏洩や通報を重罪とし、最高刑に死刑も含まれていました。
未遂や予備行為も処罰対象で、適用範囲は非常に広いものでした。
しかし、「国家秘密」の定義が不明確で、運用次第では言論や報道を制限する恐れがあると批判されました。
▶反対意見とその背景
法案には、日本弁護士連合会や報道機関から強い反対が集まりました。
主な懸念は、人権侵害や表現の自由の侵害につながることです。
また、重すぎる刑罰や、捜査権限の拡大に対する不信感も広がり、結果的に法案は廃案となりました。
主要国のスパイ防止法を比較
多くの先進国では、スパイ防止法によって国家機密の漏洩や諜報活動を厳しく取り締まっています。
日本のように、包括的なスパイ防止法が「ない国」は例外的です。
ここでは、主要国の法律とその特徴を比較し、日本との違いを明らかにします。
▶アメリカ:Espionage Act(1917年)
アメリカでは、1917年に制定されたエスピオナージ法が、スパイ行為を厳しく処罰しています。
軍事や防衛に関わる情報の漏洩は重罪で、最高刑は死刑や終身刑も科されます。
冷戦期から現在まで、多くの摘発例があります。
▶イギリス:National Security Act(2023年)
イギリスでは、2023年に国家安全法が施行されました。
これは旧「公式機密法」を全面改正したもので、サイバー攻撃や経済スパイまで幅広く対応しています。
外国情報機関への協力行為も、新たに犯罪とされました。
▶中国:反スパイ法(2023年改正)
中国の反スパイ法は、2023年の改正でさらに厳格化されました。
国家機密の定義が広がり、個人や企業にも通報義務が課されています。
外国企業への適用もあり、警戒が必要とされています。
▶ドイツ・フランス・ロシア
いずれの国も、刑法の中でスパイ行為や国家機密の漏洩を明確に犯罪として規定しています。
ドイツでは「国家反逆罪」として扱われ、終身刑の可能性もあります。
ロシアやフランスでも、重い刑罰でスパイ活動を抑止しています。
今後の焦点と懸念点は?
表現の自由とどう折り合いをつけるか
スパイ防止法が制定される際、最大の課題となるのが「表現の自由」とのバランスです。
国家機密の保護を目的とする法律が、報道や市民の調査活動を萎縮させる恐れがあります。
どこまでがスパイ行為で、どこからが正当な言論か――その線引きが極めて重要です。
過去の法案でも、この曖昧さが強く批判されました。
今後は、恣意的な運用を防ぐための明確な基準づくりが不可欠です。
各党の姿勢と今後の国会の動き
2025年現在、スパイ防止法に最も積極的なのが参政党と国民民主党です。
両党は選挙公約として法整備を掲げ、実際に国会提出の準備を進めています。
自民党や日本維新の会も、一定の理解を示しており、今後は超党派での協議が進む可能性があります。
一方、立憲民主党や共産党などは慎重な姿勢を崩していません。
今後の国会では、「必要性」と「人権保護」の両立をどう図るかが焦点になります。
国民にとってのメリット・リスク
スパイ防止法の整備によって、国家機密の流出を防ぎ、国の安全保障が強化されるというメリットがあります。
防衛・経済・技術の分野で、外国勢力による情報窃取を抑止する効果も期待されます。
その一方で、国民の言論や取材活動が制限されるリスクも否定できません。
運用を誤れば、市民社会への不信や監視社会化につながる恐れがあります。
「安全保障」と「自由な社会」の両立をどう実現するか。
この問いに対する答えが、スパイ防止法の今後を左右します。
まとめ
日本には現在、スパイ防止法が存在せず、先進国の中でも例外的な状況にあります。
1985年の法案は廃案となり、その後も法整備は見送られてきました。
しかし今、外国勢力による情報戦が現実の脅威となる中、国会では再び動きが見え始めています。
参政党や国民民主党を中心に、スパイ防止法の必要性を訴える声が強まり、与野党の一部にも前向きな姿勢が広がっています。
一方で、表現の自由や市民の権利をどう守るかという課題も避けては通れません。
この法案が、国の安全と自由をどう両立させるのか。
今後の議論をしっかりと注視していく必要があります。