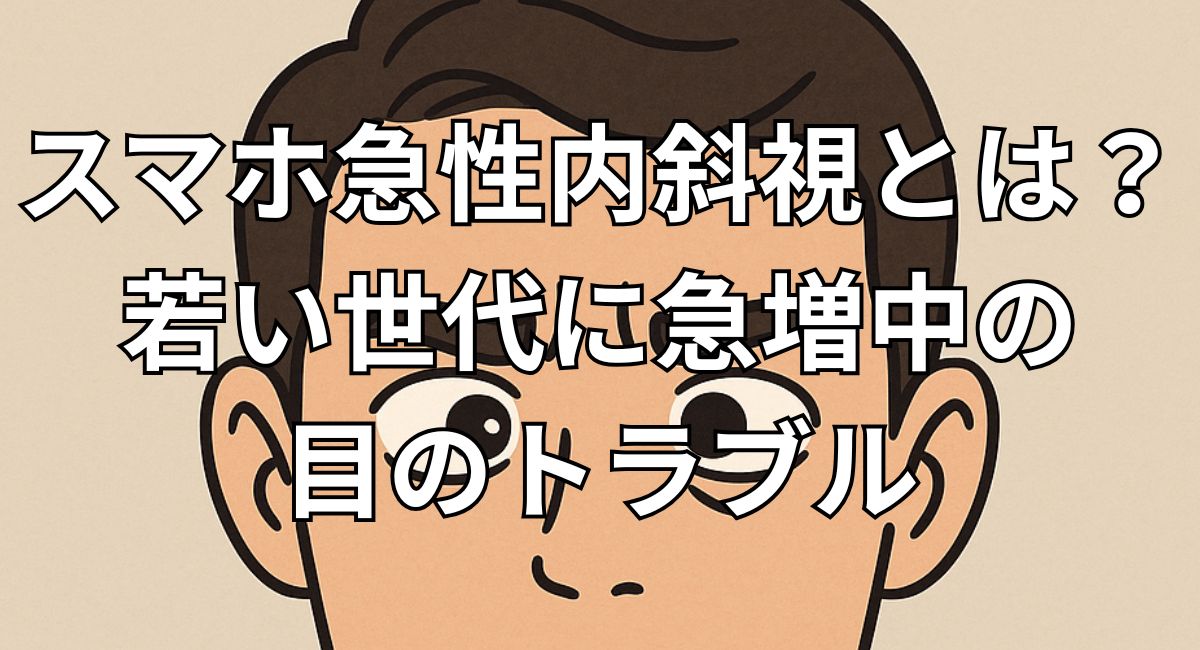最近、「スマホを見続けた後に物が二重に見える」「遠くを見るときだけ視界がズレる」といった声を聞いたことはありませんか?
それは、もしかすると「スマホ急性内斜視」という症状かもしれません。
スマートフォンやタブレット、ゲーム機などを長時間使い続けることで、目が内側に寄ってしまい、視界が不安定になる現象です。
特に10~20代の若年層を中心に、急増しているこの症状。
この記事では、スマホ急性内斜視の原因や症状、予防法について詳しく解説し、目の健康を守るためにできることをご紹介します。
スマホ急性内斜視とは
スマホ急性内斜視とは、スマホなどの画面を長時間、至近距離で見続けることによって、片方または両目が内側に寄ってしまう「内斜視」の一種です。
特に10代〜20代の若い世代に多く見られ、スマホやゲーム機の利用が生活の中心になっている現代ならではの症状といえるでしょう。
もともと内斜視は子どもに多い症状とされてきましたが、近年は「スマホが引き金」となる急性発症例が増えています。
主な症状と進行パターン
スマホ急性内斜視には、いくつかの特徴的な症状があります。
複視(物が二重に見える)
最も多いのが、突然の複視(ダブって見える)です。
- 初期段階では、「遠くを見るときだけ」複視を感じる
- スマホやゲームを控えると、一時的に改善する場合もある
- 進行すると、「近くも遠くも」常にダブって見えるようになる
日常生活に支障をきたすことも多く、放置すればさらに症状が悪化する恐れがあります。
立体視の低下
内斜視が進むと、物を立体的に見る力(両眼視機能)が弱まります。
これにより、距離感がつかみにくくなったり、車の運転やスポーツなどに支障が出ることも。
発症の原因とメカニズム
では、なぜスマホを長時間見ると、内斜視が起こるのでしょうか?
寄り目状態が続くことが要因
人間の目は、近くを見るときに自然と内側に寄ります。
これは「内直筋」という筋肉が働いて、両目のピントを合わせるためです。
スマホを至近距離で見続けることで、この内直筋が常に緊張した状態になります。
本来は、遠くを見るときに目の位置は自然に元に戻るのですが、使いすぎると脳の指令がうまく切り替わらなくなり、目が寄ったままになるのです。
スマホ急性内斜視のチェックポイント
以下のような状態に心当たりがある場合は、早めに眼科を受診しましょう。
- 遠くの看板や黒板が、ぼやけて二重に見える
- 急に片方の目が内側に寄っていると指摘された
- 目の疲れや違和感が長時間続く
- スマホを控えると症状が軽くなるが、すぐに再発する
予防のためにできること
スマホ急性内斜視は、日頃の使い方を見直すことで、十分に予防・改善が可能です。
スマホの使用時間を管理する
1時間に一度は、スマホやタブレットから目を離し、遠くを眺める習慣をつけましょう。
また、使用時間が長くなりすぎないよう、アプリで利用時間を管理するのもおすすめです。
画面との距離を意識する
スマホとの距離は、最低でも30cm以上を保つことが理想です。
寝転がって画面を顔に近づける姿勢は、特に注意が必要です。
目のストレッチや休憩を取り入れる
以下のような簡単な目のストレッチで、筋肉の緊張をほぐすことができます。
- 10秒間、遠くの風景をじっと見る
- 上下左右に目をゆっくり動かす
- まばたきを意識的に増やす
若年層に多い理由とは?
子どもや若者の目は、まだ発達途上にあります。
そのため、過剰な目の使い方により、筋肉や調節機能が影響を受けやすいのです。
また、オンライン学習やSNS、動画視聴の時間が増えたことで、10〜20代のスマホ使用はさらに加速。
「目が疲れても我慢してしまう」「症状に気づきにくい」といった傾向もあり、症状を見逃してしまうケースも少なくありません。
親や教育現場でも意識したいこと
特に小学生・中学生の場合、症状をうまく言葉で表現できないこともあります。
保護者や教師が気づいてあげることが大切です。
- 子どもが目を細めて見るようになった
- 物が見えづらいと訴えている
- 学習や集中力の低下が見られる
こうしたサインがあれば、眼科の受診をすすめましょう。
まとめ|目の健康を守るためにできること
スマホ急性内斜視は、スマートフォンやタブレットの使い方によって引き起こされる、現代特有の目のトラブルです。
特に若い世代を中心に、急増しているこの症状。
早期に気づき、スマホの使い方を見直すことで、改善や予防が可能です。
日常的に目の使い方を意識し、定期的に休ませる習慣をつけることが、目の健康を守る第一歩になります。
目に少しでも違和感を感じたら、無理をせず、早めに専門医に相談しましょう。