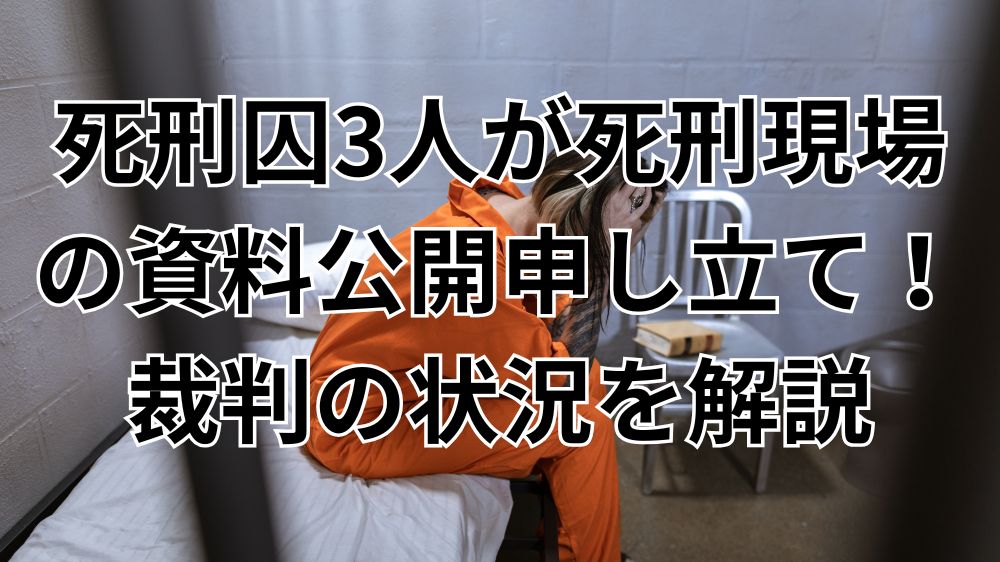死刑囚3人が死刑現場の資料公開を申し立てました。
これは、絞首刑が「残虐な刑罰」にあたるかを問う裁判の一環として、大阪地裁に提出されたもの。
死刑囚3人は「どのような設備や道具が使われているのかを明らかにすべき」と訴えました。
この記事では、死刑囚3人が起こした裁判の概要や関連する訴訟の動きまでをわかりやすく解説します。
死刑囚3人が死刑現場の資料を開示要求
2025年7月31日。
絞首刑の執行を止めるよう求める死刑囚3人が、大阪地裁に申し立てを行いました。
目的は、死刑がどのような設備や用具で行われているかを明らかにすること。
その資料を国に開示させるよう求めています。
対象は、次のとおりです。
- 東京・大阪拘置所の刑場や操作室の図面
- 絞首刑で使用される縄の材質・太さ・長さ
- 目隠しや手錠などの道具に関する資料
これらの情報は、一般には非公開で、国は、「死刑囚の心情への配慮」を理由に、公開を拒否してきました。

死刑囚3人は、「実態がわからないまま、残虐でないと判断するのは不適切」と主張しています。
死刑執行の現場は非公開な理由
日本の死刑制度では、死刑執行の現場が公開されていません。
その理由は、「死刑囚の心情への配慮」や「刑の平穏な執行を妨げるおそれがある」と国が説明。
過去に一度、2010年に、東京拘置所の刑場が、報道機関に限定公開されました。
ただしこの時も、縄や目隠し、手錠などの道具は撤去された状態での公開。
2023年には、近畿弁護士会連合会が視察を求めました。
しかし国はこれも、「死刑囚の精神的安定に影響がある」として、認めませんでした。



こうした“見えない死刑”の現状に対し、死刑囚3人が「資料を開示すべき」と声を上げたのが今回の申し立てです。
裁判の概要と背景
今回の資料開示の申し立ては、2022年に始まった裁判の一環として行われたものです。



次に、この裁判の詳細な内容と、争点について解説します。
■ 提訴の内容と目的
2022年11月、大阪拘置所に収監中の死刑囚3人が、国に対して、次のことを求める裁判を起こしました。
- 絞首刑の執行差し止め
- 執行環境に関する資料の開示(縄の材質・長さ・目隠し・手錠・刑場の図面など)
- 精神的苦痛に対する慰謝料(1人あたり1100万円、計3300万円)



死刑囚3人は、「絞首刑は、憲法第36条が禁じる『残虐な刑罰』にあたる」と主張しています。
■原告側の主張
原告である死刑囚3人の主張は、以下のとおり。
- 絞首刑は、国際人権規約や日本国憲法第36条に違反している。
- 現代の人権基準から見て、「必要最小限の苦痛」すら満たしておらず、非人道的な刑罰。
- 「残虐でない」とする国の主張を検証するためにも、具体的な資料の開示が必要である。
■被告・国の反論
一方で、被告である国(法務省側)は、過去の最高裁判例を根拠に、以下のように主張。
- 絞首刑は「残虐な刑罰には当たらない」とする判例がある(1955年、2016年など)。
- 現在の制度は「適法かつ人道的」である。
- 今回の訴え自体が「不適法」であり、棄却すべき。
■裁判の経過
2022年11月、大阪地裁に提訴されたこの裁判は、現在も審理が続いています。
似た訴訟の動き
今回の裁判と関連する、別の死刑制度に関する訴訟も進行しています。
「死刑の執行告知のタイミングは違憲か」を争点とする裁判です。
■ 当日告知の違憲性を問う裁判(大阪地裁)
死刑囚2名が、「当日告知・即日執行は憲法違反」として国を提訴。
- 大阪地裁は、当日告知に合理性があると判断し、訴えを棄却。
- 「受忍義務がないと確認したい」とする訴えも、不適法として却下。
- 国家賠償請求も、「死刑判決自体の否定に当たる」として退けられた。
■ 控訴審の判断(大阪高裁・2025年3月17日)
控訴審では、「告知を即日とすることの強制は違憲」として、地裁に審理差し戻し。
■ 最高裁への上告状況(2025年現在)
原告・被告双方が最高裁に上告。



この裁判も、今後の死刑制度運用に大きな影響を与える可能性があります。
まとめ
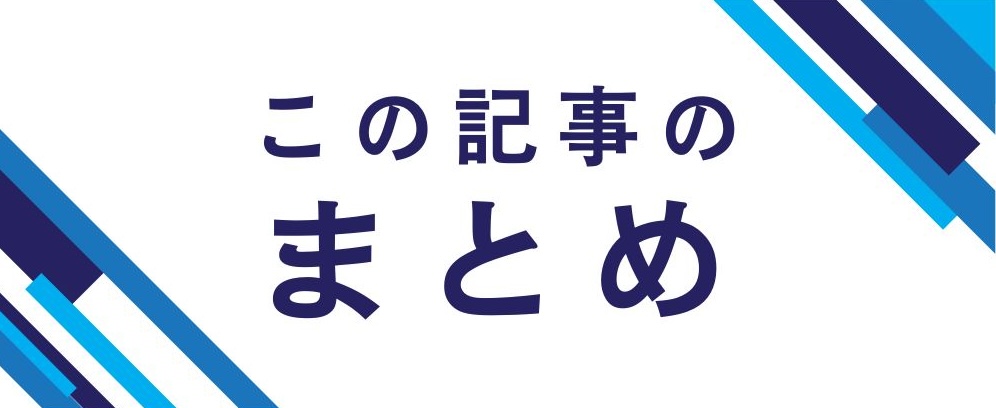
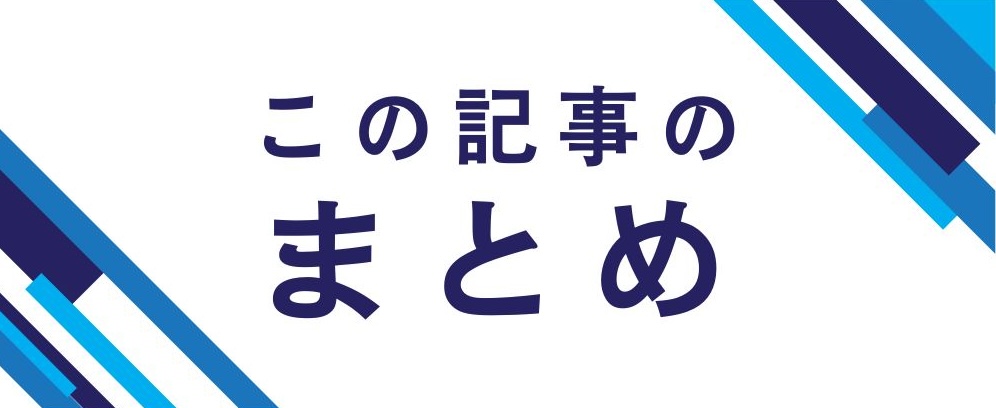
この記事では、死刑囚3人が起こした裁判とその背景について解説しました。
絞首刑に関する資料の開示を求める今回の申し立ては、日本の刑罰制度の透明性を問い直すきっかけとなっています。
要点をまとめると、以下のとおりです。
- 2022年11月、死刑囚3人が絞首刑の差し止めと資料開示を求めて提訴。
- 絞首刑は「残虐」として、憲法・国際人権規約違反を訴える。
- 被告・国は過去の判例を根拠に「残虐ではない」と反論。
死刑囚3人が起こした裁判の行方が、日本社会にとって大きな分岐点になるかもしれません。