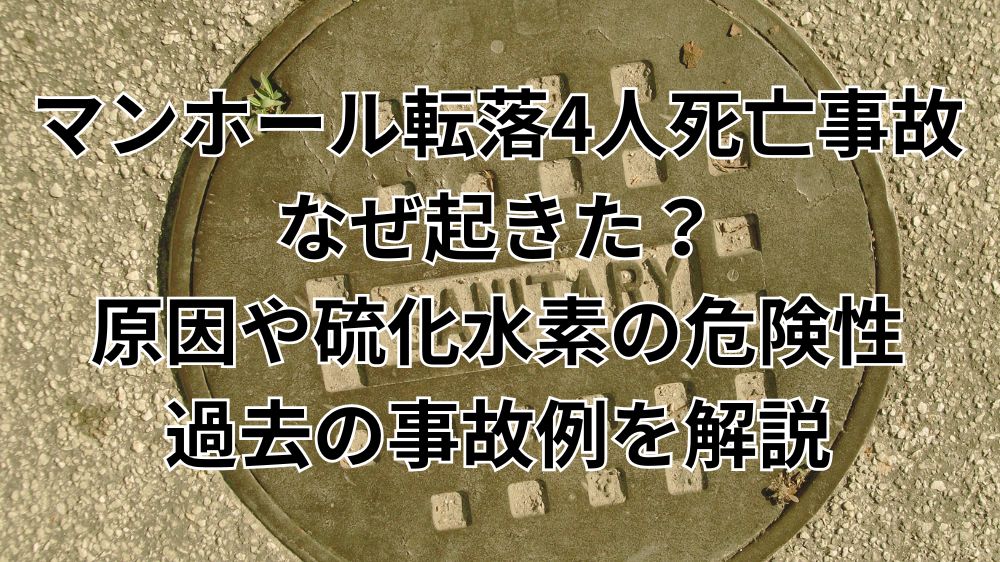埼玉県行田市で、2025年8月2日に発生した痛ましいマンホール転落事故。
作業員4人が死亡するという最悪の結果となり、原因として硫化水素の存在が浮かび上がりました。
「なぜ4人も次々と倒れていったのか?」
「安全対策はなされていたのか?」
「硫化水素の危険性とは何なのか?」
この記事では、マンホール転落4人死亡事故の経緯と背景、そして繰り返される硫化水素事故の問題点について、わかりやすく解説します。
マンホール転落4人死亡事故は何が起きた?
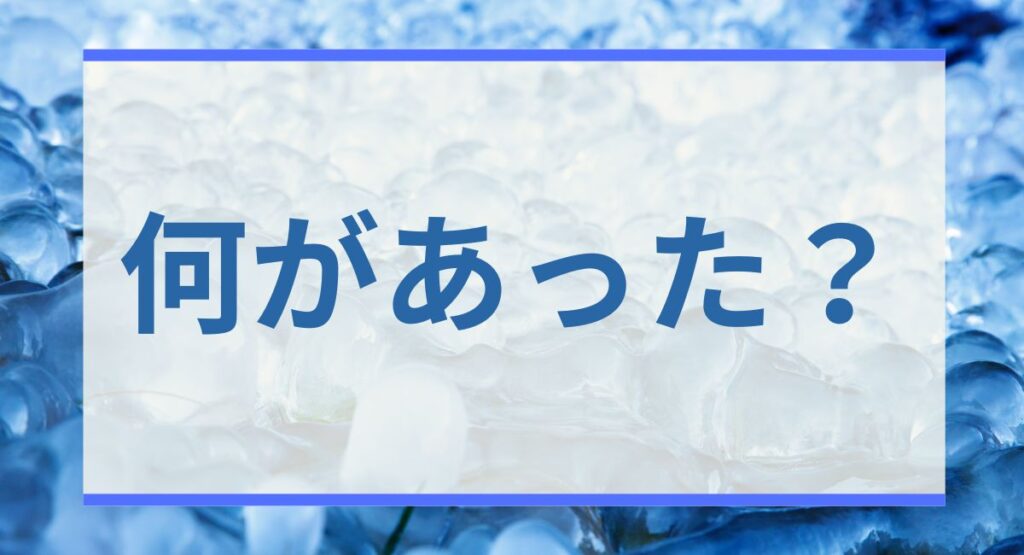
2025年8月2日、埼玉県行田市で、下水道管の点検作業中に作業員4人がマンホール内に転落。
全員が死亡する事故が起きました。
亡くなったのは、いずれもさいたま市の下水道調査会社に所属する50代の男性社員。
事故は、最初に本間洋行さん(53)がマンホール内のはしごを下りる途中に突然意識を失って転落したことから始まりました。
その後、救助に入った3人も次々と同様の状態となり、結果として4人全員が死亡。
現場のマンホール内からは基準値を大きく超える硫化水素ガスが検出されており、これが転落と死亡の原因とみられています。
マンホール転落4人死亡事故の原因
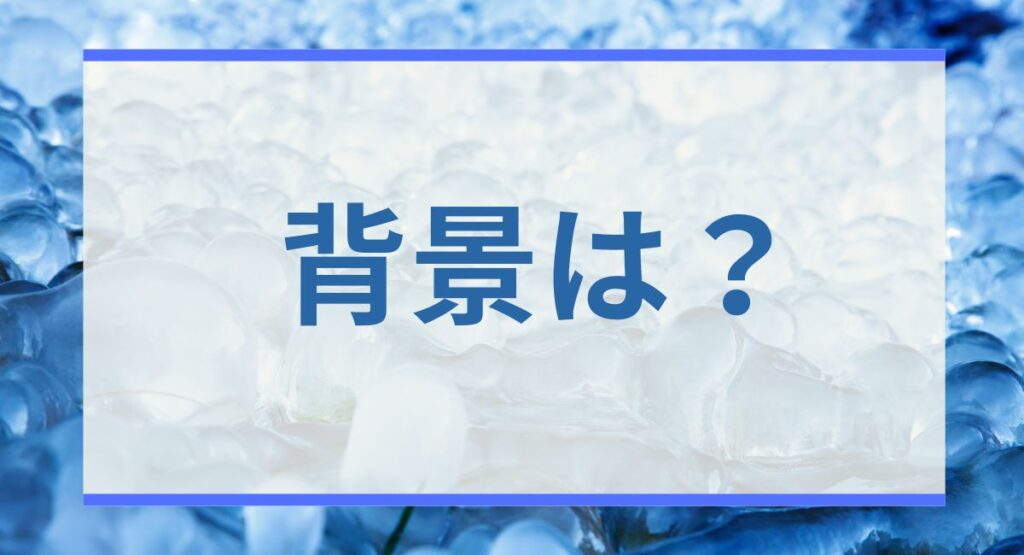
今回の事故の最大の要因は、マンホール内に充満していた高濃度の硫化水素。
作業開始時点で、1人目の作業員が下りる途中に意識を失ったことから、硫化水素を吸入した直後に中毒症状を引き起こしたと考えられます。
硫化水素は目立った外傷を残さずに意識を失わせる毒性を持ちます。
倒れた作業員を助けようとした他の3人も、同様に吸入してしまったことで、連鎖的に命を落としました。
硫化水素が発生した理由
硫化水素はなぜマンホール内に発生していたのでしょうか。
主な原因は、下水内に溜まった汚泥や腐敗した有機物です。
これらが、嫌気性菌というバクテリアの活動によって分解される過程で、硫化水素が発生します。
事故現場のマンホール内には約1.8メートルの汚水があり、そこに溜まった有機物の腐敗がガス発生の元となったと見られています。
また、換気設備や検知機器による事前のチェックが不十分だったことで、高濃度の硫化水素が長時間にわたって蓄積されていたと考えられています。
通常はチェックしないの?
マンホールや下水道管内での作業は、閉鎖空間作業とされ、法律で厳しく管理されています。
通常、作業開始前には以下の措置が求められます。
- ガス検知器での硫化水素濃度の測定
- 酸素濃度の確認
- 強力送風機による換気
- 安全装備(防毒マスクなど)の着用
労働安全衛生規則では、これらの措置は義務化されており、ガス検知器の定期点検や校正も必要。
また、急激な濃度上昇など、予測不能な事態もあるため、リスクは常に存在します。

今回の事故も、そうした「油断や見落とし」が重なって起きた可能性が高いと見られています。
硫化水素の危険性
硫化水素は、一見「卵の腐ったような臭い」で気付きやすいと思われがち。
ですが、高濃度では嗅覚を麻痺させるため、気づかないまま中毒になるリスクがあります。
濃度と影響の例:
- 10ppm:目や喉への刺激
- 50〜100ppm:吐き気、目の痛み、咳
- 100〜200ppm:嗅覚麻痺、重度の炎症
- 500〜700ppm:数分で意識喪失
- 700ppm以上:即死レベル
また、硫化水素は空気より重く、下方に溜まる性質を持つため、マンホールや地下ピットのような空間では、特に危険度が高くなります。
過去にも起きていた事故
硫化水素による死亡事故は、今回が初めてではありません。
主な過去の事故:
- 2016年・福岡市:下水施設で5人死亡
- 2019年・横浜市:下水管作業中に2人死亡
いずれのケースでも、ガス検知の不備や救助作業中の二次被害が問題視されました。



今回の行田市の事故も、「連鎖型事故」として、同様の教訓が生かされなかった事例といえます。
まとめ
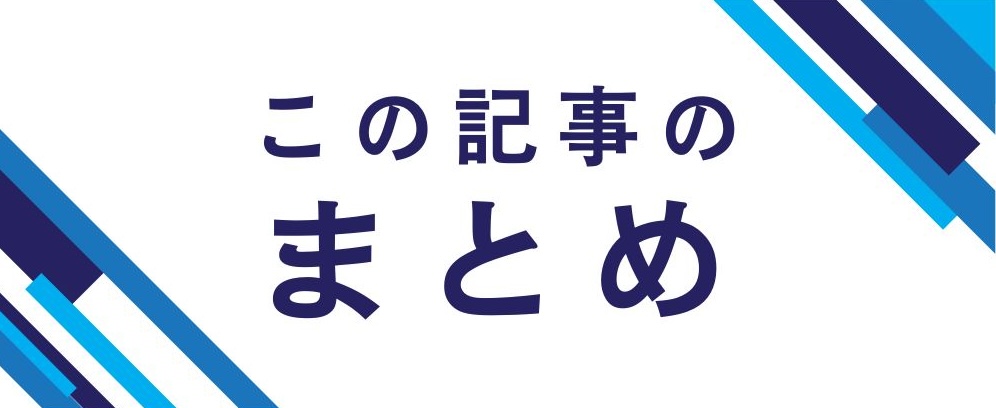
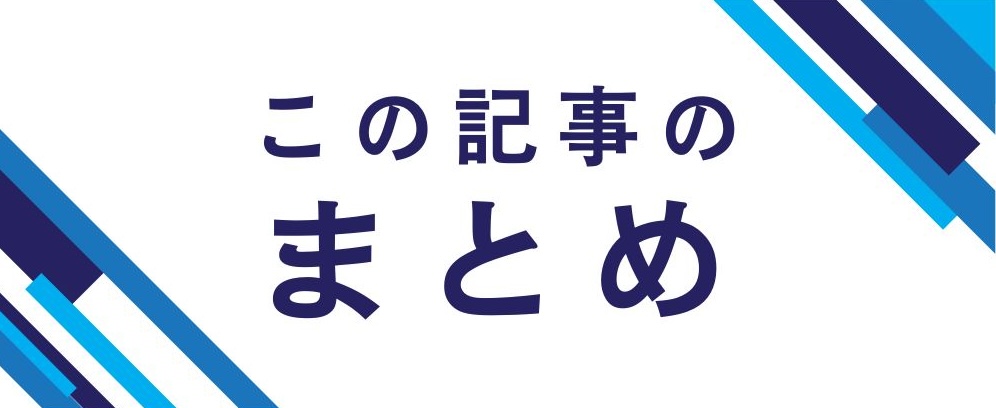
この記事では、埼玉県行田市で発生したマンホール転落4人死亡事故について解説しました。
事故の背景には、硫化水素という有毒ガスの危険性と、その管理不足があります。
この記事の内容をまとめると、以下のとおりです。
- 硫化水素が充満したマンホール内で4人の作業員が死亡
- 原因は高濃度の硫化水素吸入による意識喪失
- 同様の硫化水素事故は過去にも複数発生している
閉鎖空間での作業は、常に見えないリスクと隣り合わせです。
過去の事故から学び、安全管理を徹底することが求められています。