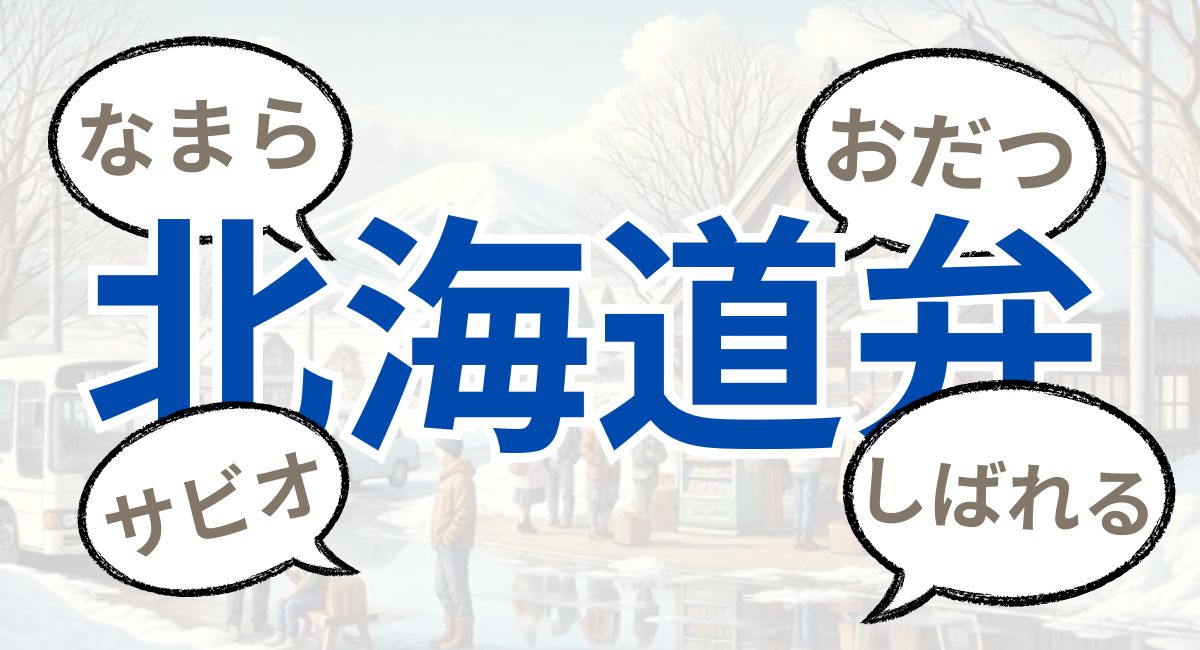北海道弁って、聞いたことはあっても実際にどう使うのかは意外と知られていませんよね。
「なまら」「しばれる」などの代表的な言葉から、道民しか知らないレアな表現まで、北海道弁には魅力がたっぷり詰まっています。
本記事では、そんな北海道弁の世界を道民目線でわかりやすく紹介していきます。
北海道旅行の前に読めば、旅がちょっと楽しくなるかも!?
そもそも北海道弁ってどんなもの?

北海道弁は、東北由来の方言をベースにしつつも、独自に発展したやさしい響きのある言葉です。
北海道弁の特徴や背景について紹介します。
東北弁とのつながり
北海道には明治以降、本州各地からの開拓民が移住してきましたが、なかでも東北地方からの入植者が多く、その影響で東北弁が北海道弁のベースになっています。
たとえば「しばれる(=凍れるほど寒い)」「あずましくない(=落ち着かない)」といった表現は、東北の言葉とも共通しています。
また、東北の中でも地域によって違う方言が、北海道に集まったことで、ひとつの新しい言葉文化として融合・定着していきました。
結果として、東北弁の名残を感じさせながらも、北海道独自のニュアンスを持つ言葉へと発展していったのです。
北海道ならではのイントネーション
北海道弁の大きな特徴のひとつが、語尾が上がるイントネーションです。
このイントネーションは、東北弁にも似た部分がありますが、北海道独自の“標準的に聞こえる方言”として、道外の人には聞き取りやすいとも言われています。
さらに、話すテンポがゆったりしているのも特徴的で、広い土地に住む人々の穏やかな生活リズムが反映されているようにも思えます。
言葉そのものの意味だけでなく、話し方からも北海道らしさを感じ取れるのが、北海道弁の面白さのひとつです。

北海道では「これ標準語でしょ?」と思って使っていた言葉が、実はローカル方言だった…ということも珍しくありません。
よく聞く!定番の北海道弁とその意味
このセクションでは、道内どこでもよく聞く定番フレーズを、意味と一緒に紹介します。
「なまら」=とても・すごく
「なまら寒い」「なまらうまい」など、強調の副詞として道民の会話によく登場します。
「超」「めっちゃ」に近い感覚で、感情や感覚を強く表現したいときに使います。



意識はしてませんが、自然と「なまら」を使っているときがありますね!
「しばれる」=凍えるように寒い
「しばれる」は、ただの寒さではなく、氷点下で空気が乾いていて刺すような寒さを表す表現です。
冬の北海道をリアルに感じるには、この言葉がぴったりです。
「あずましくない」=落ち着かない、居心地が悪い
人混みの中や騒がしい場所、またはなんとなく気を使う場面などで感じる違和感や不快感を表現します。
精神的にも物理的にも「落ち着かない」状態を指します。
空間が狭い、人が多い、ガヤガヤしてる…そんなときに使います。



「人の家で寝るなんて、あずましくないっしょ!」(=人の家で寝るなんて、落ち着かないよね)という感じで使います。
意外と知られてない?ローカル色強めの北海道弁
道民同士なら通じるけれど、他県の人には「???」となりがちな、コアな北海道弁をご紹介します。
「おだつ」=はしゃぐ・調子に乗る
テンションが上がってふざけすぎたり、場の空気を読まずに目立とうとしたときに使われる言葉です。
「おだつなよ!」と親や先生に注意された経験がある道民も多いはずです。
子どもがテンション上がってると「おだつな!」って注意されたりします。
「つっぺ」=鼻血止めのティッシュ
鼻血が出たときに丸めたティッシュを鼻に詰める——そのティッシュのことを「つっぺ」と呼びます。
また、「つっぺ」は鼻に限らず、すき間を塞ぐような小さな詰め物全般を指すこともあります。
実用的で的確な、北海道らしい生活密着ワードです。



小学生の頃「つっぺしてな!」ってよく言われていました。
「ぼっこ」=棒のこと、とくに小さい棒
細い枝や割り箸サイズの木の棒を「ぼっこ」と呼ぶのは、北海道ならでは。
語感がちょっとかわいらしくて、子ども同士の会話にもよく登場します。



木の枝を見つけると「いいぼっこ拾った〜!」ってよく言ってました
「サビオ」=絆創膏のこと(商品名由来)
ニチバンがかつて販売していた絆創膏の商品名が、北海道では今も一般名詞化。
道民にとっては当たり前の単語ですが、全国的にはすでに販売終了しているため通じにくいことも。
サビオは元々ニチバンの絆創膏の商品名。
今は販売終了しているものの、北海道ではそれが一般名詞化しています。他県では「バンドエイド」や「カットバン」が主流なので、通じない可能性大。



「サビオある?」って聞いたら「なにそれ?」って言われたことがあります(笑
「したっけ」=別れ際の「そしたらまたね」
もともとは「そうしたら」を意味する接続語でしたが、北海道では別れ際のあいさつとして定着しました。
語感がやわらかく、親しみのこもった表現として今も日常的に使われています。
「したっけ」は「そしたら(またね)」という意味の挨拶。会話の終わりに使うことが多く、親しみを込めた北海道らしい別れの言葉です。



仲が良い相手に使うことが多いです。
電話の最後に「したっけね〜」って言うのが定番です。
まとめ|北海道弁は道民のアイデンティティ
北海道弁は、ただの方言というより、道民らしさや土地の空気を感じさせてくれる“文化”のひとつです。
普段の生活の中に自然と溶け込んでいて、会話にやわらかさや親しみを与えてくれます。
「なまら寒いね」「あずましくないな〜」といった言葉を通して、道民同士の心の距離がぐっと縮まる。
そんな感覚があるのも、北海道弁の魅力ではないでしょうか。
道外の方にもぜひこの温かい方言の世界に触れてもらい、北海道をもっと身近に感じていただけたら嬉しいです。
旅行や出張で北海道を訪れた際には、現地の人との会話の中に北海道弁を探してみてください。
耳をすませば、旅がもっと味わい深くなるはずです。