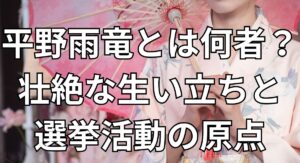最近、SNSやネットニュースで「背乗り(はいのり)」という言葉を見かけることが増えました。
「あの人は背乗りの疑いがある」といった投稿もあり、なんとなく不気味に感じる人も多いのではないでしょうか。
しかし、意味や背景を知らないままでは、正しく理解することも、対策を講じることもできません。
この記事では、「背乗り」の意味、由来、使い方、さらには防止策や関連法規についても詳しく解説します。
背乗りの意味は
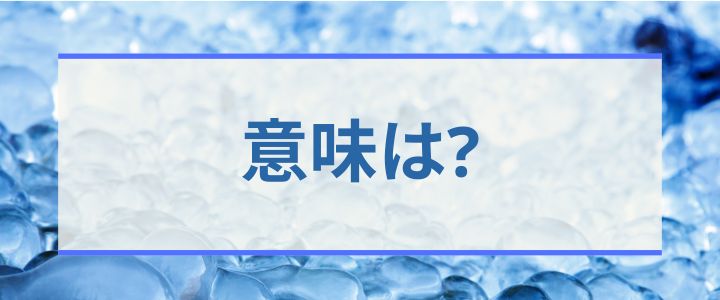
「背乗り(はいのり)」とは、工作員や犯罪者が他人の身分や戸籍を乗っ取って、その人物になりすます行為を意味します。
これは警察用語であり、日本語では「なりすまし」とも言われます。
たとえば、死亡または行方不明になった人の戸籍を不正に取得し、まるで自分のもののように使うケースがあります。
さらに深刻なケースでは、対象者を拉致・殺害して、その身分証を奪うという凶悪犯罪も存在します。
このような背乗りは、スパイ活動や組織的な犯罪で多く使われてきました。

特に、北朝鮮の工作員による背乗り事例が日本国内でも確認されており、社会的な関心が高まっています。
背乗りの由来は?


背乗りという言葉の由来は、相撲や格闘技における「相手の背中に乗る」という動作に由来しています。
つまり、相手の背中に便乗するように、その人物の身分に入り込み、成り代わるイメージから来ています。



背乗りは、警察や公安関係者の間で使われる隠語的な表現でしたが、近年は一般のメディアでも使用されるようになりました。
背乗りの具体例は?
ここでは、過去に実際に発生した背乗りの事例をいくつか紹介します。
- 北朝鮮の工作員が、失踪した日本人の戸籍を利用し、日本国内で活動していた。
- 海外のスパイが、死亡した人物のパスポートを偽造し、第三国で活動を行っていた。
- 組織的な詐欺グループが、孤独死した高齢者の身分を乗っ取り、年金を不正受給していた。



このように、背乗りは国家の安全保障や個人の財産に関わる重大な問題です。
背乗りと身分証明書の厳格化
背乗りを防ぐために、各国では身分証明書の発行や確認プロセスを厳格化しています。
日本でも、マイナンバーカードやICチップ付きパスポートなど、本人確認の厳格化が進められています。



また、行政機関や金融機関では、顔認証や生体認証を用いた本人確認の導入も進んでいます。
背乗りの防止策
個人としても、背乗り被害に遭わないよう対策が必要です。
- 戸籍謄本や住民票の管理を徹底する
- マイナンバーを不用意に他人に見せない
- SNSに個人情報を載せない
- 不審な郵送物や訪問者に注意する
- 定期的に信用情報を確認する



少しの注意が、背乗りの深刻な被害を防ぐ大きな一歩になります。
背乗りに関する法律
日本では、背乗り自体を明確に定義した法律は存在しませんが、以下の法律で取り締まられることがあります。
- 戸籍法違反
- 有印公文書偽造罪
- 詐欺罪
- 不正アクセス禁止法



特に、背乗りによって、他人になりすまして利益を得た場合は、詐欺罪や公文書偽造罪が適用され、重い刑罰が科される可能性があります。
背乗りとサイバーセキュリティ
近年では、背乗りがネット上でも行われるようになっています。
SNSアカウントやメールアドレス、オンラインバンキングなど、個人情報が狙われています。
このような「デジタル背乗り」には、以下の対策が有効です。
- 強固なパスワードを設定する
- 二段階認証を導入する
- フィッシング詐欺に注意する
- セキュリティソフトを導入する



オンライン上でも、本人確認が重要視される時代になっています。
まとめ
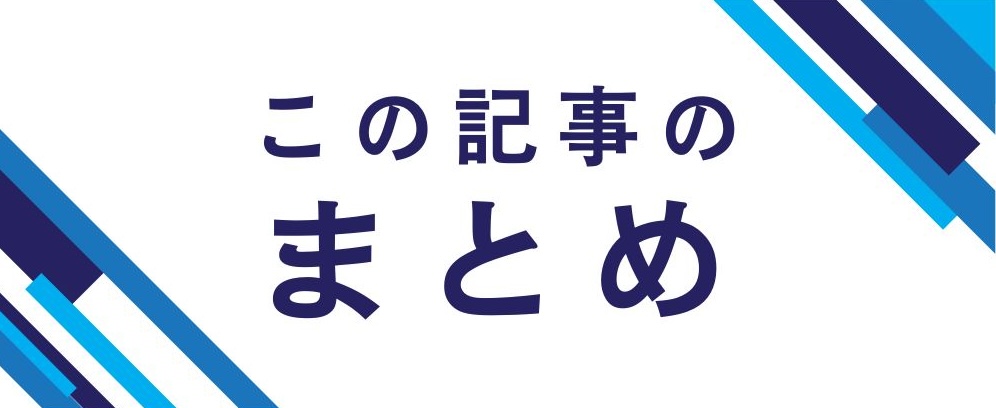
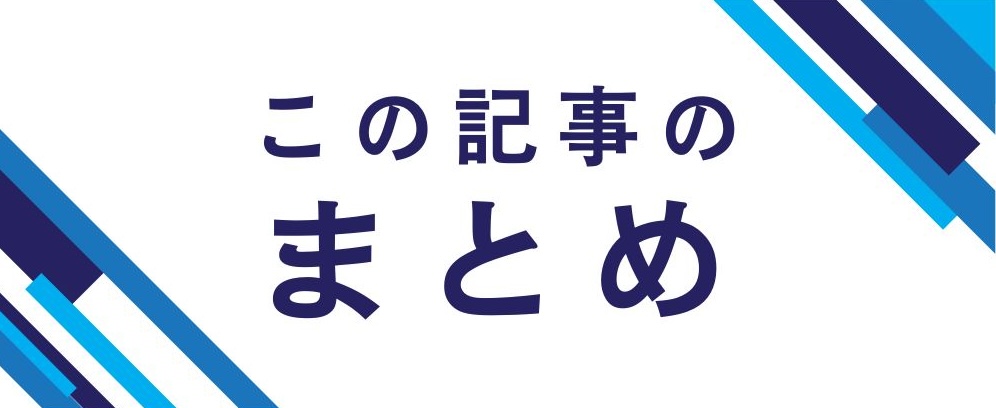
この記事では、背乗りについて解説しました。
背乗りは、他人の身分を乗っ取る危険ななりすまし行為です。
この記事の内容をまとめると、以下のとおりです。
- 背乗りは他人の戸籍や身分を不正に乗っ取る行為
- 由来は「相手の背中に乗る」ことから
- 個人の情報管理が最大の防止策
背乗りから身を守るためには、日常からの注意と、正しい知識が欠かせません。