都内の火葬場の多くを運営する東京博善が、火葬料金の実質値上げを発表。
背景には、中国資本の影響が強まる経営構造の変化があります。
この記事では、
- 東京博善の現社長・野口龍馬氏の経歴
- 中国資本が入った経緯・理由
- 火葬料金の変化が私たちの生活に与える影響
を、詳しく解説します。
東京博善の現社長は誰?

東京博善の代表取締役社長は、野口龍馬氏です。
野口龍馬のプロフィールと経歴
野口龍馬さんは、1974年7月9日生まれ。2025年8月24日現在で51歳です。
1997年に株式会社廣済堂へ入社。
情報システム部門を中心にキャリアを積み上げてきました。
社内の開発推進部長やソリューション部長を歴任し、経営企画やDXに関する専門性を深めていきました。
そして2023年に東京博善の取締役に就任。
2025年6月に代表取締役社長に昇格しています。
廣済堂グループ内でのキャリアとは
野口氏のキャリアの特徴は、廣済堂グループ一筋で歩んできた点にあります。
情報ソリューション事業の中核を担い、社内のIT戦略や業務効率化に貢献してきた実績があります。

こうした背景から、経営とITの両輪で火葬場事業を推進する役割が期待されています。
東京博善の社長交代の流れ
最近の東京博善の社長交代について見てみましょう。
根岸千尋、和田翔雄から野口龍馬へ
東京博善では、近年社長人事が活発に動いています。
- 2022年4月:廣済堂専務の根岸千尋氏が社長に就任
- 2023年6月:副社長の和田翔雄氏が社長に昇格
- 2025年6月:野口龍馬氏が社長に就任



短期間で複数回のトップ交代があり、経営の安定性や方向性に注目が集まっています。
社長交代が意味するもの
この短期間での交代は、親会社・廣済堂ホールディングスの経営方針の変化、そして外資の影響を強く反映したものと見る向きもあります。
社長交代は、事業戦略の転換や収益構造の再構築の兆しとも受け取れます。
東京博善に中国資本が入ったと言われる理由
東京博善に中国資本が入ったとされる背景には、親会社である廣済堂ホールディングスの経営体制の変化があります。
東京博善は、廣済堂ホールディングスの子会社として火葬場事業を担っており、その親会社の資本構成が大きく変わったことが直接の要因です。
廣済堂株の売却と増資の背景


かつて、廣済堂ホールディングスは、麻生グループをはじめとする日本国内の資本が中心となって運営されていました。
その後、中国出身の実業家・羅怡文(ら・いぶん)氏が会長を務める企業グループが、廣済堂の株式を大量に取得。
さらに、第三者割当増資などを通じて持株比率を40%以上に引き上げ、実質的な経営権を掌握しました。
羅怡文会長とはどんな人物か


羅怡文氏は、中国出身の実業家で、これまで日本国内でさまざまな企業投資を手がけてきた人物です。
廣済堂ホールディングスの会長に就任してからは、傘下企業の経営にも深く関与しており、東京博善の運営にも間接的に影響を及ぼしています。
このようにして、東京博善は経営的には廣済堂ホールディングスを通じて中国資本の影響下にある企業となりました。
中国資本化と火葬料金の変化


東京博善は、都内23区にある火葬場のうち、6カ所を運営しており、シェアはおよそ70%。
この高い公共性を持つ火葬場の運営が、現在では中国資本の影響を受ける体制になっていることに、各方面から懸念の声が上がっています。
中国資本が関与する中での変化
中国資本が経営に関与し始めてから、最も注目されているのが火葬料金の相次ぐ値上げです。
東京博善は、2025年度末をもって、区民が低価格で火葬を受けられる制度「区民葬」から離脱する方針を発表。
これにより、火葬料金は以下のように変更されます。
- 従来の価格(区民葬価格):5万9600円
- 改定後の価格(通常価格):8万7000円
- 実質的な値上げ額:2万7400円
区民にとっての影響
火葬は、誰にとっても必要不可欠なインフラです。
しかし、今回の価格改定により、多くの市民が突然大きな負担を強いられる可能性があります。
政治や行政の対応も注目
このような状況を受けて、都議会や区議会では、火葬料金の価格の透明性確保や条例による規制を求める声が高まっています。
特に、「公共性の高い火葬場運営を民間、それも外資に任せてよいのか?」という疑問は根強く、今後の行政対応が問われています。
まとめ
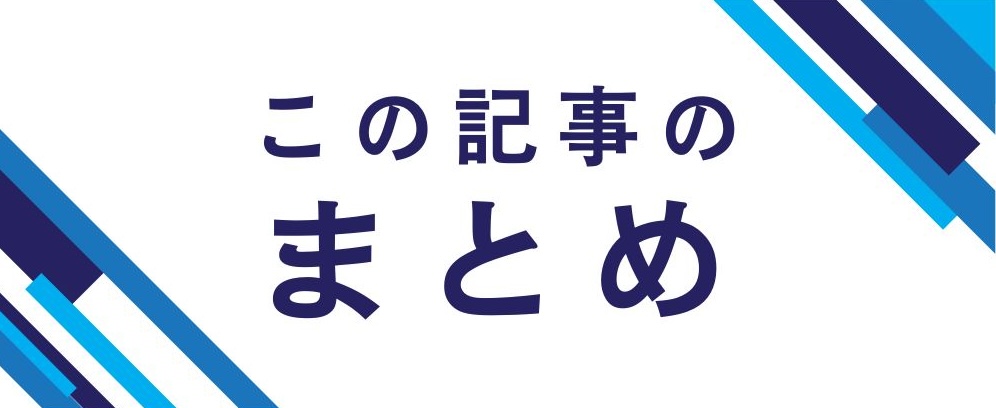
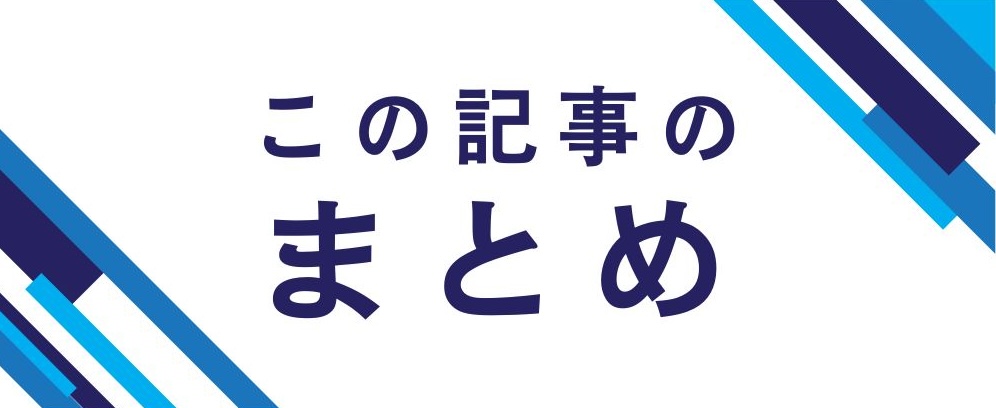
この記事では、東京博善の社長情報と、中国資本が入った理由、そして火葬場運営の今後について解説しました。
- 東京博善の社長は、廣済堂出身の野口龍馬氏
- 経営悪化を受け、親会社・廣済堂に中国資本が流入
- 実質的に外資の支配下で、火葬料金の値上げが続く
- 2026年度から区民葬制度から離脱し、火葬料は大幅アップ
- 火葬場という公共インフラへの外資参入に懸念の声
火葬場のあり方は、今後ますます社会的な議論が求められるテーマとなるでしょう。
市民一人ひとりが、この問題に関心を持ち、行政の動向にも注目していくことが重要です。
