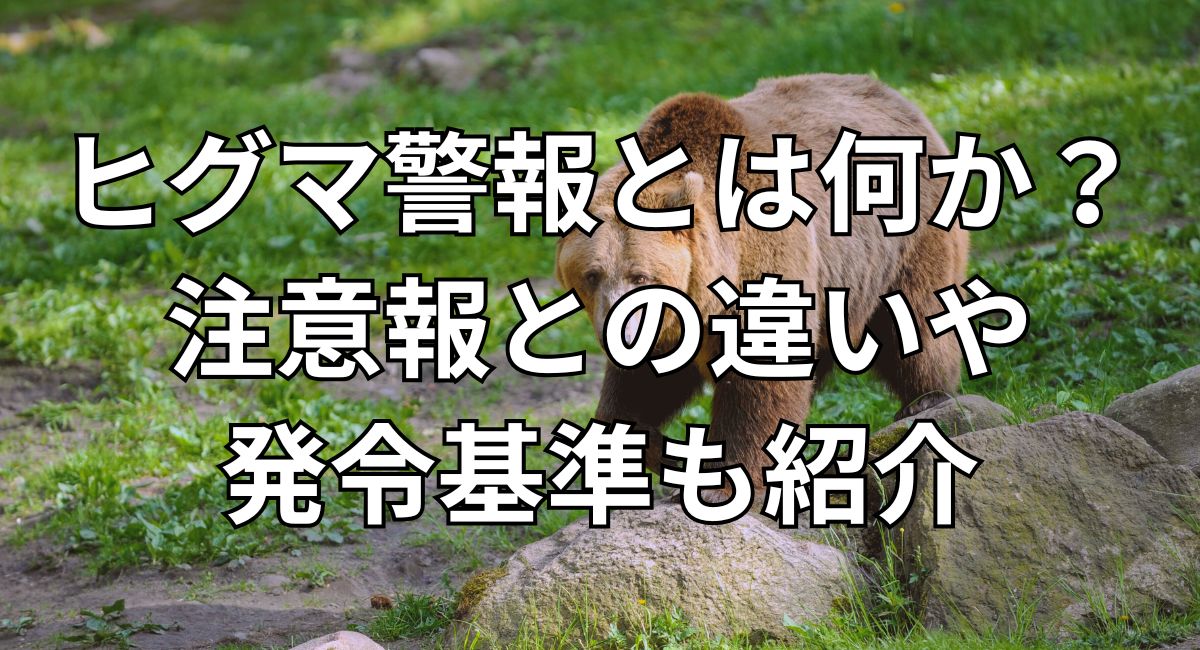北海道では、人身被害や市街地へのヒグマ出没が深刻化しています。
そんな中、道民や観光客の安全を守るために設けられた制度が「ヒグマ警報」です。
この記事では、ヒグマ警報の仕組みや発令条件、住民に求められる行動をわかりやすく解説します。
ヒグマ警報の概要と目的
ヒグマ警報とは、北海道で新たに導入された重要な制度です。
市街地など人が多く暮らす場所で、ヒグマによる人身事故が発生した際に発令されます。
ヒグマ警報が発令されると、住民や観光客へ強い注意喚起が行われ、安全確保のための具体的な行動が求められます。
ヒグマ警報の制度概要
- ヒグマ警報は、北海道が独自に運用する緊急警報制度です。
- 市街地や住宅街で、ヒグマによる人身事故(けがや死亡事故)が起きた場合に発令されます。
- 通常の「ヒグマ注意報」とは異なり、ヒグマ警報は、より重大な状況を対象としています。
つまり、ヒグマ警報は「実際に被害が発生した後」に出される強い警戒レベルです。
ヒグマ警報の主な目的
ヒグマ警報が発令される目的は、次の3つにまとめられます。
- 道民や観光客の命を守るため、人身被害を防ぐこと
- 外出自粛やゴミ管理など、ヒグマを引き寄せない生活行動を促すこと
- 自治体や関係機関が、ヒグマ捕獲や住民安全対策を迅速に進める体制づくり
ヒグマ警報があることで、住民や観光客が状況を正しく理解し、適切な行動をとる助けになります。
また、自治体もヒグマ対策をよりスムーズに進められるようになります。

ヒグマ警報は、ただの注意喚起ではなく、「命を守るための緊急措置」として位置づけられています。
このように、ヒグマ警報は北海道に暮らす人すべてに関わる大切な制度です。
最近では、制度運用の実績も増え、より多くの人に知ってもらうことが重要になっています。
ヒグマ警報とヒグマ注意報の違い
ヒグマ警報とヒグマ注意報は、どちらも北海道で運用されているヒグマ対策の制度です。
しかし、発令される条件や目的、住民に求められる行動は大きく異なります。
ヒグマ警報とヒグマ注意報の比較表
| 項目 | ヒグマ注意報 | ヒグマ警報 |
|---|---|---|
| 発令条件 | ヒグマの目撃増加や農作物被害 | 市街地でヒグマによる人身事故(死傷事故)が発生 |
| 目的 | ヒグマとの遭遇防止、予防的注意喚起 | 人身被害の拡大防止、強い警戒と行動制限 |
| 発令頻度 | 比較的高い(毎年複数回) | 非常に低い(2025年福島町が初) |
| 主な住民等への要請 | ゴミ管理・注意喚起 | 外出自粛・生活行動の制限・厳重な警戒 |
ヒグマ警報の特徴と注意報との違い
ヒグマ警報は、実際に市街地などでヒグマによる重大事故が発生した場合のみ発令されます。
これに対し、ヒグマ注意報は目撃件数の増加や農作物被害など「今後事故が起きる恐れがある段階」で発令されます。
つまり、ヒグマ警報はヒグマ注意報よりも発令基準が厳しく、「命の危険が差し迫っている非常事態」であることを示すものです。
また、ヒグマ警報発令時には、
- 不要不急の外出を控える
- 生活圏でのゴミ管理を徹底する
- ヒグマ出没エリアへの立ち入りを避ける
など、通常の注意報よりも一段階強い行動制限が求められます。
ヒグマ警報は、北海道に暮らす私たちにとって命と暮らしを守るための大切な制度です。
普段から「ヒグマ注意報」と「ヒグマ警報」の違いを理解し、万が一に備えておきましょう。
ヒグマ警報の発令条件と基準
ヒグマ警報は、次のような状況で発令されます。
- 市街地でヒグマによる人身事故(死傷)が発生した場合
- 同じ地域でヒグマの出没が繰り返され、定着の恐れがある場合
- ヒグマが威嚇や攻撃性を示す場合
発令地域は事故や出没があった市町村が中心で、必要に応じて周辺にも広がります。
期間は原則1か月間ですが、状況次第で延長されることもあります。
住民に求められる行動
ヒグマ警報が発令された場合、住民や観光客は次の行動を徹底してください。
- 不要不急の外出を控える
特に夜間や早朝はヒグマと遭遇しやすいため注意が必要です。 - ゴミや生ゴミを適切に管理する
ゴミを放置するとヒグマを誘引します。収集日以外のゴミ出しは厳禁です。 - 山林や河川敷、公園などへの立ち入りを控える
生活圏だけでなく自然歩道や森にも近づかないようにします。 - ペットフードや食べ物を屋外に置かない
食料品や餌は屋内で保管し、外には出さないようにします。 - ヒグマの目撃情報や痕跡を見かけたら通報する
自治体や警察に速やかに連絡し、自分で対処しないことが重要です。 - ヒグマを見かけても刺激しない
追い払おうとせず、静かにその場を離れます。 - 自治体から発信される最新情報を確認する
防災無線や広報、公式サイトで正しい情報をこまめにチェックしてください。
ヒグマ警報発令中は、一人ひとりの注意と行動が事故防止につながります。
実際の発令事例と運用状況
ヒグマ警報は、制度として整備されてからしばらく発令例がありませんでした。
しかし、2025年7月、北海道福島町で重大な事故が発生し、初めて正式にヒグマ警報が出されました。
2025年 福島町での発令事例
- 発令日:2025年7月12日
- 発令期間:7月12日〜8月11日予定(延長の可能性あり)
- 対象区域:福島町全域
主な対応内容
- 住宅街や周辺地域でのパトロール強化
- ゴミ出しルールの再徹底や指導
- ハンターや警察によるヒグマの捜索・捕獲
- 防災無線や広報車による情報発信
- 観光施設や登山道の利用制限
ヒグマ警報発令直後は、ヒグマ注意報との違いがわかりにくいという声もあり、
道や自治体は今後、わかりやすい周知方法や制度の改善を進める方針です。
ヒグマ遭遇時の対処法
ヒグマ警報が出ている時はもちろん、普段から万が一に備えて対処法を知っておくことが大切です。
ヒグマと遭遇した場合、以下の行動を冷静に守りましょう。
- 走らず、落ち着いてゆっくり後退する
走って逃げるとヒグマの追跡本能を刺激します。 - 自分が人間だと静かに伝える
声をかけたり、ゆっくり手を振ったりして、ヒグマに存在を知らせます。 - 子グマには絶対に近づかない
近くに母グマがいるため、非常に危険です。 - 距離が縮まる場合は強気に威嚇する
身体を大きく見せたり、複数人なら固まって行動します。 - クマ撃退スプレーを持っている場合は活用する
接近された時は顔や鼻先に向けて噴射します。 - 攻撃を受けた場合は防御姿勢をとる
うつ伏せになり、首や頭を腕で守ります。リュックがあれば背中にかぶせて使います。



ヒグマ遭遇時は「落ち着くこと」と「ゆっくり後退」が最優先です。
焦らず、安全を第一に行動してください。
まとめ
ヒグマ警報は、北海道独自の制度であり、市街地でヒグマによる人身事故(死傷)が発生した場合に発令される緊急警報です。
通常のヒグマ注意報とは異なり、より深刻な状況で発動され、住民や観光客に対し、外出自粛やゴミ管理の徹底、生活行動の見直しが求められます。
実際に2025年、福島町で初めてヒグマ警報が発令され、町全域で厳重な対策が講じられました。
ヒグマ警報発令時はもちろん、普段からヒグマ遭遇時の正しい対処法を身につけ、安全意識を持つことが重要です。
「ヒグマ警報=命を守るための合図」
その意味をしっかり理解し、行動に移しましょう。