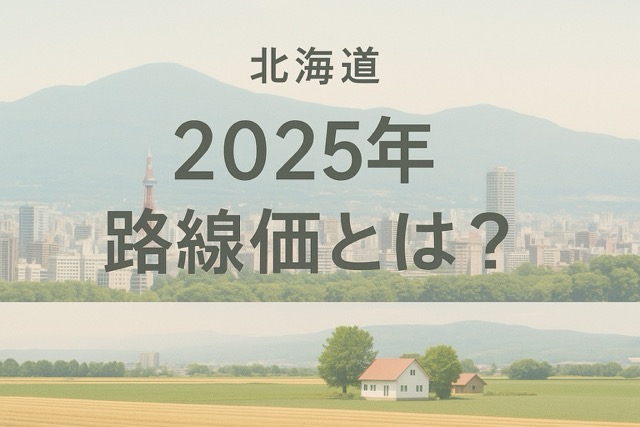「路線価って聞いたことあるけど、よくわからない」
そんな方に向けて、2025年の最新データをもとに、北海道の路線価の見方・使い方をやさしく解説します。
相続や不動産に関わる前に、知っておきたい基礎知識をまとめました。
2025年の北海道の注目ポイント
2025年の北海道の路線価は、前年比2.4%の上昇となり、10年連続の上昇を記録しました。
しかし、上昇率は前年の5.2%から大きく減速し、全国平均(2.7%)も下回りました。
札幌圏の勢いに陰りが見られたのが特徴です。
札幌市中央区・平岸エリアでは上昇幅が前年から10ポイント前後縮小。建築費高騰や金利上昇による買い控えが背景にあります。
一方で、富良野市では観光需要の高まりから、北の峰線通りが前年比30.2%上昇し、全国でも2番目に高い伸びを記録しました。
深川市では、本町通りの路線価が前年比10.0%減の9千円となり、全道で唯一1万円を下回りました。商店街の後継者不足や空き店舗の増加が影響しています。
全体では、札幌・苫小牧・小樽など9署で上昇、16署で横ばい、5署で下落。
札幌ステラプレイス前は20年連続で最高路線価を更新し、774万円に到達しました。
都市部と地方の二極化が進み、地域ごとに明暗が分かれた年となりました。
路線価とは?意味と特徴を解説
路線価とは何か、いつ発表されるのか、どこで確認できるのかを解説します。
路線価とは
路線価(ろせんか)とは、道路に面した土地1㎡あたりの価格のことです。
国税庁が、毎年決めて発表しています。
この価格は、相続税や贈与税の計算に使うためのものです。
つまり、税金を正しく計算するために、国が目安として決めた「土地の値段」だと考えてください。
実際に土地を売ったり買ったりするときの価格とは違います。
そのため、不動産の売買価格よりも少し低めに設定されるのが一般的です。
おおよそ、不動産会社などが提示する価格の8割くらいを目安に作られています。
発表日はいつ?
路線価は、毎年7月1日に国税庁から発表されます。
ただし、この価格のもとになっているのは、その年の1月1日時点の土地の状況です。
たとえば、2025年の路線価は、2025年1月1日時点の地価をもとに決められ、それが7月1日に発表されました。
どこで確認できる?
路線価は、国税庁のホームページで誰でも無料で調べることができます。
「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」というページにアクセスしましょう。
都道府県や市町村を選んでいくと、地図上に道路ごとの数字が表示されます。
たとえば「300C」と書かれていれば、1㎡あたりの価格が30万円で、Cは借地権に関する記号です。
スマホからでも見られるので、気になる土地がある方は一度確認してみると良いでしょう。
路線価はどうやって決められる?
路線価は、どのようにして決まっているのでしょうか。
ここでは、その決定プロセスや毎年変動する理由、よく似た「公示価格」との違いについて解説します。
路線価の決め方
路線価は、国税庁が毎年決定しています。
その際には、不動産鑑定士などの専門家が評価した土地の価格や、実際の取引事例、公示価格など、さまざまな情報が使われます。
また、周辺の地価や地域の特徴、都市の発展状況なども考慮されます。
たとえば、新しい駅ができた、商業施設がオープンした、というようなニュースも影響します。
こうした複数の要素をもとに、そのエリアで標準的な道路に面した土地の1㎡あたりの価格が決まるのです。
なぜ毎年変わるのか
路線価は、毎年1月1日時点の地価をもとに決められるため、年ごとに変動します。
地価が上がれば、路線価も上がる傾向にあります。
たとえば、再開発が進んでいるエリアや観光客が増えている地域では、土地の需要が高まります。
逆に、人口が減っている地域や、空き地・空き家が増えている場所では、下がることもあります。
その地域の経済状況や生活環境の変化が、路線価に大きく影響しているのです。
公示価格との違い
よく似た言葉に「公示価格(こうじかかく)」があります。
これは、国土交通省が発表する「土地取引の目安となる価格」です。
一方で、路線価は「税金を計算するための価格」。
目的が異なるため、同じ土地でも価格に差があります。
一般的には、路線価は公示価格の8割程度に設定されます。
つまり、実際に不動産会社などで売られる価格よりも、少し低めということです。
この違いを知っておくと、土地の価値を正しく判断する手助けになります。
どう使う?相続・贈与・土地活用に活用
路線価は、土地の評価だけでなく、日常生活にもさまざまな形で関わっています。
ここでは、実際にどんな場面で使われるのかを、具体例を交えて紹介します。
相続税・贈与税の評価に使う
もっとも代表的な使い方が、相続税や贈与税の計算です。
土地を相続したとき、その価値をどう評価するかによって、支払う税額が変わってきます。
評価の方法は、以下のような計算式が基本です。
路線価 × 補正率 × 土地の面積(㎡) = 評価額
たとえば、路線価が20万円、補正率が0.85、土地の面積が200㎡だった場合、
20万円 × 0.85 × 200㎡ = 3,400万円
これが、相続税を計算するための「土地の評価額」となります。
土地の形状や奥行きによって補正率が変わることもありますが、基本の流れはこの通りです。
売買の参考にもなる
路線価は、不動産を売る・買うときの参考価格としても使われています。
もちろん、実際の売買価格は市場の需要や個別の条件で決まりますが、
「この土地はいくらくらいの価値があるのか」という目安にはなります。
とくに、周辺に似た条件の土地がない場合などには、路線価が一つの判断材料になります。
不動産会社との交渉や、価格の妥当性を確認するときにも役立ちます。
将来の資産計画に活用
路線価は、資産形成や相続設計を考える際の指標としても有効です。
たとえば、複数の土地を所有している場合、それぞれの路線価を確認することで、
「どの土地がどれくらいの価値を持っているか」が見えてきます。
それによって、分割の仕方や売却の順番を考える手助けにもなります。
また、土地を担保にローンを組むときや、将来の納税資金を準備するときにも役立ちます。
日頃から路線価をチェックしておくことで、いざという時に慌てずに済みます。
路線価の見方と調べ方
「路線価図ってどう見ればいいの?」
そう思う方も多いかもしれませんが、ポイントを押さえれば意外とシンプルです。
ここでは、実際の図面で使われている表記の意味や、調べ方をわかりやすく解説します。
路線価図の読み方
路線価図とは、道路ごとに1㎡あたりの評価額が数字で示されている地図のことです。
たとえば、「200C」と書かれていた場合、
- 数字「200」は、「その道路に面する土地の1㎡あたりの評価額が20万円」であることを意味します。※単位は「千円」で表記されています。
- アルファベット「C」は、借地権の割合(借地権割合)を示しています。
このように、道路に沿って記号が並んでおり、土地がどの道路に面しているかを確認することで、評価額がわかる仕組みです。
借地権割合の意味
路線価図に記載されているアルファベットは、借地権の割合を表します。
これは、その土地を他人に貸している場合に、どのくらいの価値として評価するかを示すものです。
記号ごとの目安は以下の通りです。
| 記号 | 借地権割合(評価の目安) |
|---|---|
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
たとえば「C」と書かれていれば、その土地を借りている人の権利は「土地全体の70%の価値」として評価されます。
借地や貸地の評価を行う際には、この割合をもとに計算します。
設定されていない地域は?
すべての地域に路線価があるわけではありません。
人口が少ない地域や、商業活動が活発でないエリアでは、路線価が設定されていない場合もあります。
その場合には、「評価倍率方式」という別の方法で土地の評価を行います。
評価倍率方式では、市町村ごとに設定された倍率を使って、固定資産税評価額に倍率をかけて評価額を求めます。
こちらも国税庁の同じサイト内で調べることが可能です。
まとめ
路線価とは、税金を計算するために使われる「土地の基準価格」です。
毎年7月に国税庁から発表され、相続税や贈与税の評価に欠かせない情報となっています。
2025年の北海道では、札幌圏の上昇ペースが鈍化する一方で、富良野市のように観光需要を背景に大きく上昇した地域もありました。
都市と地方で明暗が分かれる結果となり、地域の将来性や生活環境の変化が価格に大きく影響していることがわかります。
調べ方や見方も意外と簡単で、国税庁のサイトを使えば誰でも確認できます。
土地を相続する予定がある方や、不動産の価値を知りたい方は、ぜひ活用してみてください。
正しく理解し、きちんと準備することが、将来の安心につながります。
毎年の路線価をチェックする習慣を、今から始めてみませんか?