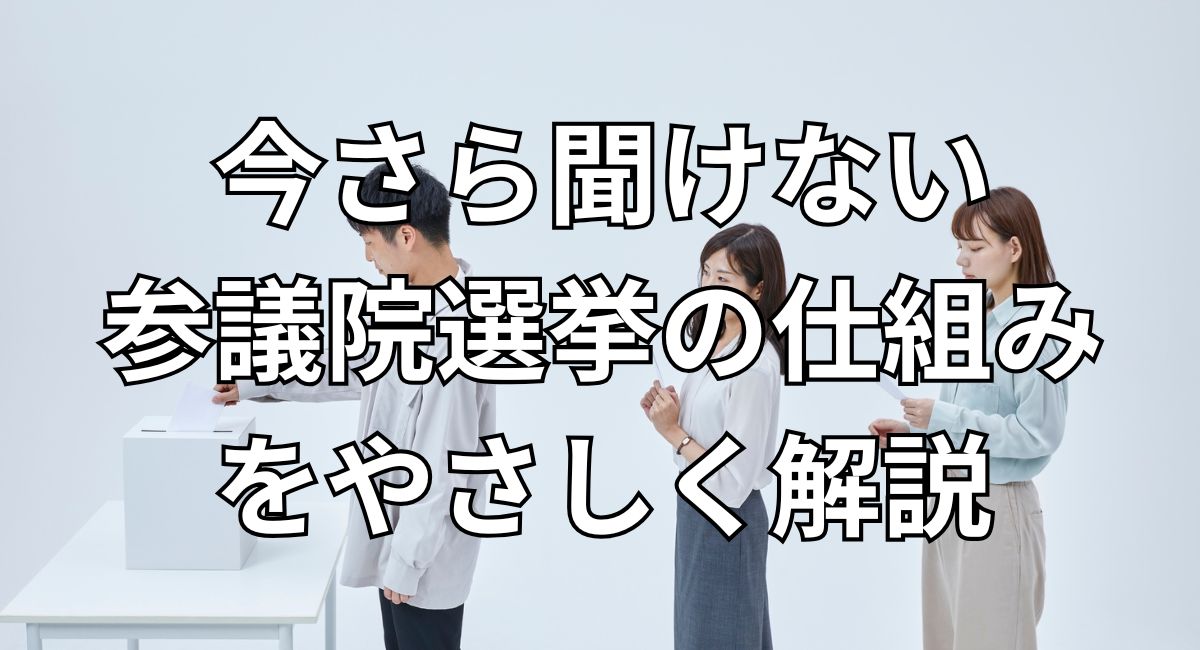「選挙ってなんだか難しそう…」「比例代表って聞いたことあるけど、よくわからない」
そう思っている人、意外と多いのではないでしょうか。
でも、2025年7月20日に行われる参議院選挙は、私たちの生活や未来に深く関わる大切な機会です。
この記事では、選挙初心者でもわかるように、参議院選挙の仕組みや比例代表についてやさしく解説します。

この記事を読み終わる頃には、「ちょっと選挙に行ってみようかな」と思えるはずです。
参議院選挙はなぜ行われる?
参議院選挙が行われる理由を、初心者にもわかりやすく説明します。
任期が終わるから選挙をするんだよ
参議院議員の仕事は「6年間」と決まっています。
けれども、全員が同じタイミングでやめると、国会の仕事が止まってしまいます。
そこで、「3年ごとに半分ずつ入れ替える」という仕組みになっています。
これを「任期満了による改選(かいせん)」といいます。
今回の参議院選挙も、このルールにのっとって行われるものです。



3年前に選ばれた議員のうち半分が、もう一度選び直されることになります。
248人をどうやって選ぶの?
参議院の定数は、全部で248人です。
でも、この248人全員を一度に選ぶわけではありません。
選び方には2つの方法があります。
- 選挙区で選ぶ人 → 148人
- 比例代表で選ぶ人 → 100人
選挙区とは、日本全国を45の地域に分けて、その中で候補者に投票する方法です。
比例代表とは、全国単位で政党に投票し、その得票数に応じて議席が決まる選挙の仕組みです。
つまり、選挙では「自分の住んでいる地域の代表」と「政党全体への応援」の2つの視点で議員を選ぶことになるんです。



次に、実際の選挙の仕組みを見てみましょう!
参議院選挙の仕組み
参議院選挙の仕組みを理解するには、まず「2票を投じる」というルールを知っておくことが大切です。
参議院選挙の投票のとき、私たちは、2つの投票用紙を受け取ります。
- 1つは「選挙区」の候補者に投票する紙
- もう1つは「比例代表」として政党や候補者の名前を書く紙
まず、「選挙区」では、自分の住んでいる地域から立候補している人の中から1人を選びます。
次に、「比例代表」の票では、全国をひとつの大きな選挙区として考え、政党の名前や比例代表として立候補している人の名前を書きます。



つまり、1人1人の票が「政党の力」にも「候補者個人の当選」にもつながる、工夫された仕組みなのです。
選挙区制ってなに?
参議院選挙では、「選挙区制」という仕組みで議員を選ぶ方法があります。
これは、日本全国をいくつかの地域に分けて、それぞれの地域から、代表を選ぶ選び方です。
たとえば、北海道には北海道選挙区があります。
北海道の中で立候補している人の中から、「この人に国会で働いてほしい!」と思う人を1人選んで投票するわけです。
このように、自分の住んでいる地域の代表を決めるのが選挙区制の特徴です。
都道府県ごとに選べる人数は異なり、人口の多いところほど、当選できる人数も多くなっています。
選ばれた議員は、自分の地域の声を国に届けるために働きます。



地域の事情をよく知る人が選ばれることが多いため、私たちの生活に身近な政策を考えてくれる存在になるのが、この選挙区制の大切な役割です。
比例代表制ってなに?
比例代表制は、全国をひとつの大きな選挙区として、政党ごとに投票して議員を選ぶ参議院選挙の仕組みのひとつです。
投票用紙には、政党名を書くことも、比例代表として立候補している候補者の名前を書くこともできます。
この投票結果によって、各政党がどれだけの議席(=議員の数)をもらえるかが決まります。
たとえば、ある政党が全国の票の20%を集めた場合、その政党には約20%分の議席が与えられることになります。
さらに、同じ政党の中で「誰が当選するか」は、その候補者の名前がどれだけ書かれたか(得票数)で決まるんです。
つまり、政党を応援する気持ちと、この人に国会で活躍してほしいという思いの両方を、1票で届けられる仕組みです。



このように、比例代表制は「個人」だけでなく「政党全体の考え方」も重視して選ぶという意味で、とても重要な選挙の仕組みなんですね。
まとめ
参議院選挙は、私たちの未来に関わる大切なイベントです。
でも、難しいと思っていた選挙の仕組みも、「選挙区制」と「比例代表制」の2つを理解すれば、ずっとわかりやすく感じられたのではないでしょうか。
選挙区制では、自分の地域の代表を選びます
比例代表制では、応援したい政党や考えに共感する候補者を選べます
どちらの1票も、私たちの生活や社会に直接つながる、大切な選択です。
1票が集まれば、社会は動きます。
初心者でも仕組みを知れば、選挙はぐっと身近になります。
今年の参議院選挙、まずは「投票に行ってみる」ことから、一歩を踏み出してみませんか?