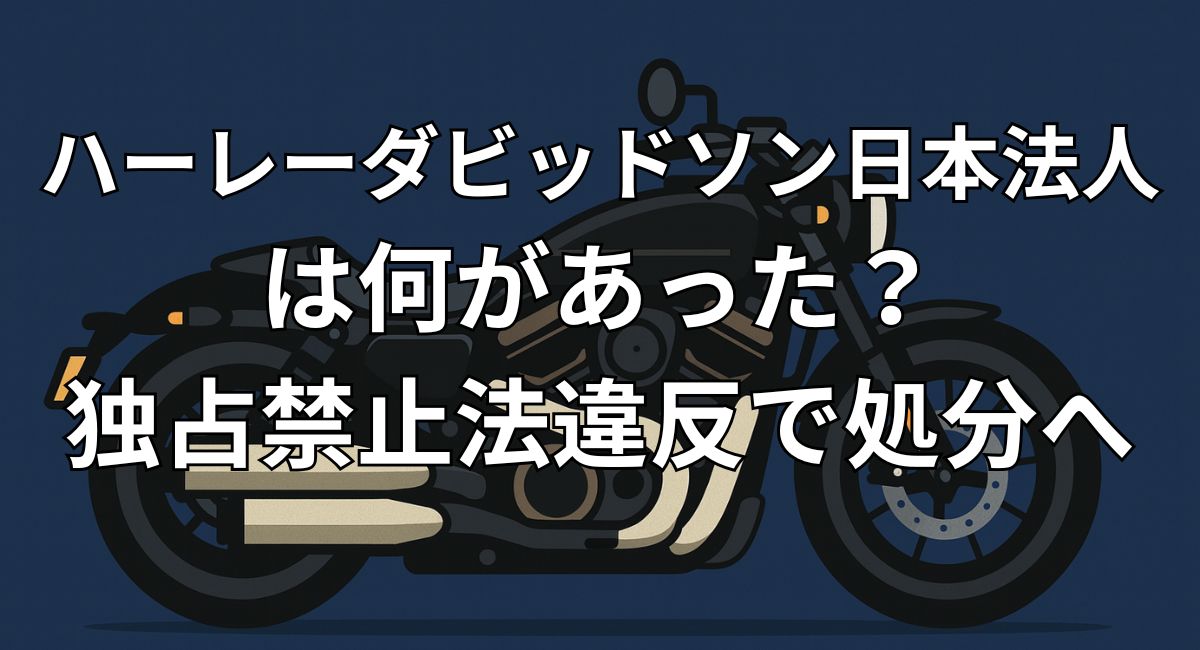公正取引委員会は、ハーレーダビッドソン日本法人に対し、独占禁止法違反の疑いで処分を行う方針を固めました。
ハーレーダビッドソン日本法人は、販売店に対して過剰な販売ノルマを課していたとされています。
背景には、メーカーと販売店との間にある力関係や、業界全体の構造的な問題があると考えられます。
この記事では、ハーレーダビッドソン日本法人に対する排除措置命令の内容と経緯を、初心者にもわかりやすく解説していきます。
何があった?

ハーレーダビッドソン日本法人に対する処分内容と、その背景について解説します。
公取委が処分決定
公正取引委員会は、ハーレーダビッドソン日本法人に対し、排除措置命令と約2億円の課徴金納付命令の処分案を通知しました。
これは、同社の行為が独占禁止法に違反する「優越的地位の乱用」に該当すると判断したためです。
「優越的地位の乱用」とは?
優越的地位の乱用とは?
力関係で優位に立つ企業が、取引先に対して不当に不利な条件を一方的に押し付ける行為
これは、独占禁止法で明確に禁止されている行為です。
今回のケースでは、ハーレーダビッドソン日本法人が、販売店に対して過剰な販売ノルマを設定し、
さらに「ノルマを達成しなければ契約を打ち切る」といった圧力をかけていたとされています。

こうした行為が、「優越的地位の乱用」にあたると判断された理由です。
排除措置命令って何?
排除措置命令とは、公正取引委員会が独占禁止法に違反した企業に対して出す命令です。
排除措置命令の目的は、違法行為をすぐにやめさせ、同じ問題が再発しないようにすることです。
今回のような場合、排除措置命令では以下のような措置が含まれます。
- 過剰な販売ノルマの設定をやめること
- 販売店との契約内容を見直すこと
- 社内規程や再発防止研修の実施
- 違法行為をやめたことを社内外に周知すること



この命令に従わない場合、企業にはさらなる行政処分や刑事罰が科される可能性もあります。
課徴金って何?
課徴金とは、独占禁止法に違反した企業に科される金銭的なペナルティです。
違法行為によって得た利益を「返還させる」意味合いがあります。
今回、ハーレーダビッドソン日本法人には、約2億円の課徴金が科される見込みです。
この金額は、違反行為の内容や継続期間、影響の大きさなどに応じて決まります。



課徴金は、公正な市場環境を守るための抑止力としても機能しています。
問題となった行為
ハーレーダビッドソン日本法人が販売店に対して行っていた問題行為を具体的に見ていきます。
これらが「優越的地位の乱用」と判断された根拠となっています。
過度な販売ノルマ設定
ハーレーダビッドソン日本法人は、2023年1月以降、通常の販売能力を超えるような過剰な販売ノルマを販売店に一方的に課していました。
ノルマが達成できないと、「契約を打ち切る可能性がある」といった圧力をかけるケースも確認されています。
このような行為は、販売店が逆らいづらい立場にあることを利用した一方的な取引条件の押し付けとみなされます。
ディーラーの“自社買い”強要
ノルマ未達成を避けるために、販売店の従業員や法人名義でバイクを購入させる「自社買い」が行われていました。
これは、ハーレーダビッドソン日本法人が直接命じたというより、販売店が契約維持のためにやむなく実施したケースが多いとされています。
その結果、在庫として抱えたバイクは「新古車」として安く売るしかなくなり、利益が圧迫される状況が発生しました。
販売店の経営崩壊リスク
「自社買い」によって、多額の資金が一時的に必要となり、資金繰りが悪化した販売店も出てきました。
中には、経営が立ち行かなくなり、廃業やハーレーダビッドソン日本法人との契約を打ち切られた店舗も存在します。



このような一連の流れが、独占禁止法違反として重大視された背景です。
公取委の命令と今後の対応
公正取引委員会が示した命令の内容と、ハーレーダビッドソン日本法人が取るべき対応について整理します。
今回の処分案の中心は、独占禁止法に違反する行為を即時に停止し、再発を防ぐための体制づくりを行うことです。
具体的には、以下の対応が求められます。
- 過剰な販売ノルマの設定をやめること
- 社内規程や運用ルールを整備すること
- 再発防止のために社員教育・研修を徹底すること
さらに、ハーレーダビッドソン日本法人は、こうした措置を販売店や全社員に明確に通知し、理解させる責任があります。
そのためには、取締役会での決議や内部管理体制の強化も不可欠です。
なお、公正取引委員会からの排除措置命令に従わない場合には、刑事罰の対象となる可能性もあります。



命令を軽視せず、迅速かつ確実に対応することが求められています。
業界への影響
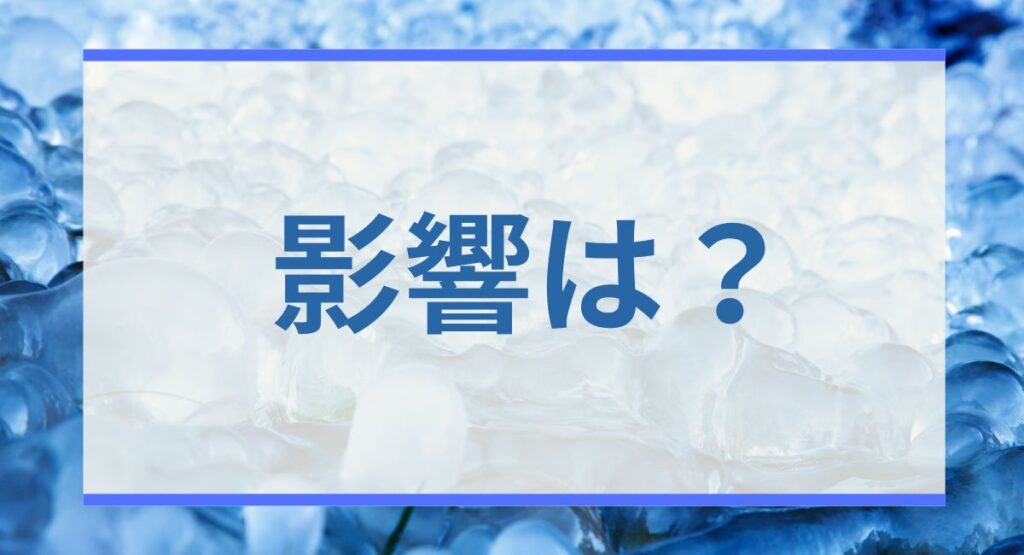
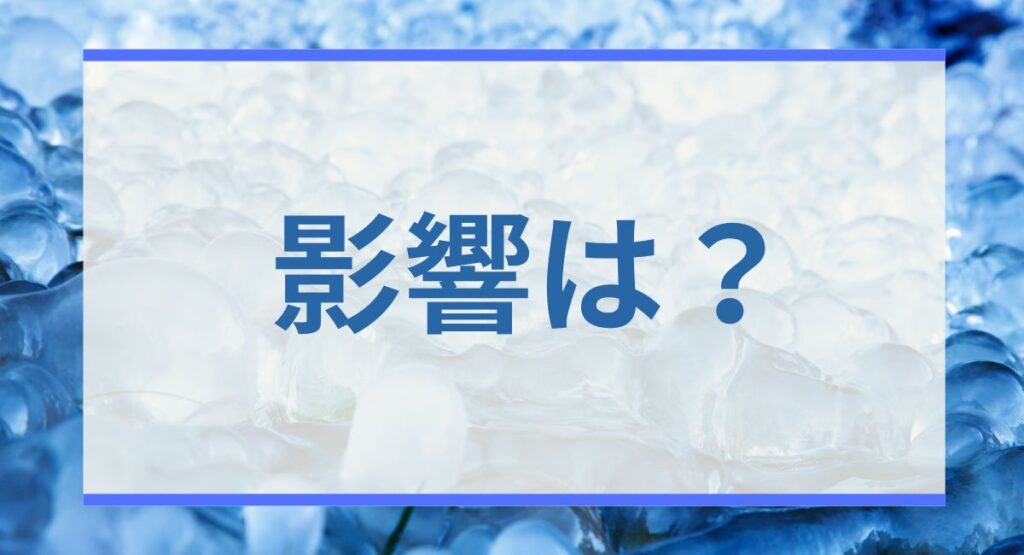
ハーレーダビッドソン日本法人による独占禁止法違反の疑いは、バイク業界全体に大きな影響を与える可能性があります。
今回の問題をきっかけに、販売手法や契約のあり方が見直される動きが広がるかもしれません。
ディーラー契約に新たな基準
今回の事案を受けて、ハーレーダビッドソン日本法人を含むバイクメーカー各社と販売店の契約条件が再検討される可能性があります。
メーカー側による過度なノルマや圧力が問題視される中で、対等な関係性を保つ契約内容が求められる時代に入ったといえます。
販売店側にとっては、内部監査やコンプライアンス体制の強化が、今後ますます重要になります。
市場価格への波及
強制的な「自社買い」によって、多くの新古車が市場に出回った結果、供給過剰となり、バイクの中古価格が下落する恐れがあります。
これは、ハーレーダビッドソン日本法人だけでなく、他社製品の中古市場や新車販売にも波及する可能性があります。
結果として、消費者の購入行動や市場全体の価格形成にも影響を及ぼすことが懸念されます。
他ブランドにも警鐘
今回のケースは、ハーレーダビッドソン日本法人だけの問題ではありません。
他のバイクメーカーでも、同様に「優越的地位の乱用」に該当する取引慣行がないか、業界内での見直しが必要です。
公正取引委員会の動きが他ブランドへの抑止力となり、業界全体の健全性が問われる局面に入ったといえるでしょう。
まとめ
ハーレーダビッドソン日本法人による行為は、独占禁止法違反(優越的地位の乱用)に該当すると判断されました。
その結果、以下のような問題が明らかになっています。
- 販売店に対して、達成困難な過剰ノルマを一方的に設定
- ノルマ未達成時に「契約打ち切り」を示唆し、心理的圧力をかける
- 販売店側が「自社買い」で在庫処理を迫られ、資金繰りが悪化
- 経営難・廃業に追い込まれた販売店も発生
- 排除措置命令と課徴金(約2億円)の処分案をHDJに通知
- 現在は意見聴取手続き中で、今後正式に処分が決定される見通し
- 命令に従わない場合は、さらなる行政処分や刑事罰の可能性も
- 再発防止策の実施と体制強化が求められる
- 業界全体で販売手法や契約のあり方を見直す動きが加速する可能性
- 販売店は、内部管理・リスク対策を見直す好機でもある
ハーレーダビッドソン日本法人の一件は、一企業の問題にとどまらず、バイク業界全体にとって大きな転換点となり得ます。
「当たり前」とされてきた慣行を見直し、公正な取引と持続可能な関係構築が求められる時代に入ったといえるでしょう。